この記事は「民法における無効と取消の違い・追認・その効果」について行政書士試験対策向けにわかりやすく解説しています。

無効・取消し
無効
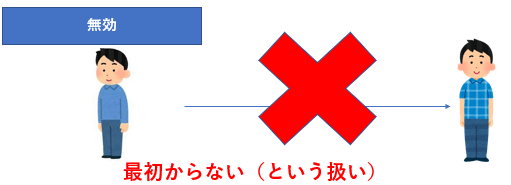
無効とは、法律行為の効力が初めから生じないことをいいます。
例えば、AB間の売買契約が公序良俗違反で無効である場合(公序良俗に反する契約は無効という民法がある)、契約は初めから効力を生じることはありません。
無効と言う状態は、A・Bはもちろん、A・B以外の第三者も無効を主張することができます。
また、無効の主張に期限はありません。
無効な行為は、追認によっても、その効力を生じませんが、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなされます(119条)。
ただし、この「新たな行為」も法律行為の有効要件が満たされなければ(無効のままであれば)法律行為は当然有効とならないため、新たにまた無効となります。

取消し

取消しとは、有効な法律行為を取消しという意思表示によって、はじめから効力を生じない(無効)こととすることをいいます(121条)。
取消権者
取り消すことができる行為は、行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含みます。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者(120条1項)、錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人(120条2項)に限り、取り消すことができます。
(cf)無効の場合は第三者も誰でも主張できる

要復習
取消し(取消権)の消滅時効
取消できる権利、つまり取消権にも消滅時効があります。
主観的期間:追認をすることができる時から5年間(を経過すると消滅)
客観的期間:行為の時から20年(を経過すると消滅)
取り消すことができる行為は、追認する(この契約を認めます!ということ)と有効となり、
以後、取り消すことができなくなります(122条)。

無効はめっちゃ強い!とイメージしましょう。
なので、たとえば意思表示の場合でも、
通謀虚偽表示では原則無効、ですが 錯誤等では「取消できる」(弱め)なのです。
通謀虚偽表示は非常に悪質ですので無効ですが、
錯誤はありえるっちゃありえる話なので「一応有効だけど取消できるよ」くらいの扱いということですね!
無効・取消しの効果
最初から契約がなかったことになる
例えば、売買契約を締結した場合、当該契約の無効・取消しにより、最初から契約がなかったのと同じことになります。
原状回復義務を負う
当事者は、相手方を原状に復させる義務(原状回復義務)を負います(121条の2第1項)。
※例外:意思無能力者や制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還義務を負うのみ(121条の2第3項)。
※例外:無償行為に基づく債務の履行(贈与等)として給付を受け、無効又は取り消すことができるものであることを知らなかった者も、現に利益を受けている限度において、返還義務を負えばよい(121条の2第2項)。
この「現に利益を受けている限度」とは、費消したり、滅失・損傷した部分を差し引いた現存する利益をいいます。
例えば、被保佐人AがBに自動車を売却し、受領した代金をすべてギャンブルに使ってしまったとしたら、現存する利益はないことになり、代金を返還する必要はありません。しかし、すべて生活費に充てたとしたら、その分の生活費の支出を免れ、形を変えて利益が現存することになり、代金を返還する必要があります。
追認
追認の意義

追認とは、一般に、ある行為を有効なものとして確定させることをいいます。
追認には、
・無効な行為の追認
・取り消すことができる行為の追認
・無権代理行為(代理の記事で説明)があります。

「取消なのか(無効になるか)」「有効のまま継続させる」のかわからない状態です。
そのような状態だと社会における契約や取引の安全性が非常に不安定になります。
なので「追認」という「有効確定」の切り札を民法では用意しているのです!
文字通り、追認とは「追って認める」ということなので
「一応有効だけど取消になるかもしれない契約を(後から追って)認めて有効を確定させる」のが追認の効果になります!
無効な行為の追認
無効な行為は、追認によっても効力を生じません(119条本文)。(無効は有効だと思い込んでいた契約がそもそもなかったことになるので、そもそも追認自体ができないはず。)
※例外:当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなされます(119条ただし書)。
例えば、通謀虚偽表示による売買契約は無効ですが、当事者が無効であることを知って追認をしたときは、追認した時点で新たな行為(契約)とみなされます。
しかし新たな行為も通謀虚偽表示の状態のままであると新たにまた無効になります。
取り消すことができる行為を追認すると、再度取消することはできない

取り消すことができる行為は、取消権者が追認したときは、以後、取り消すことができません(122条)。

そもそも追認する意味がなくなりますよね。
先ほども言いましたが「追認」は「取消で無効になるか、有効のままなのかわからない法律行為を確定的に有効化する」ことなので、
当然のことです。追認した後は、該当取引に関しては取消することはできません。
追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じません(124条1項)。ただし、次の①②の場合には、追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にすることを必要としません(124条2項)。
①法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をするとき。
②制限行為能力者(成年被後見人を除く。)が法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得て追認をするとき。
法定追認
法定追認とは、取り消すことができる行為について、一定の事実が存在する場合に当然に追認したものとみなされることをいいます(125条)。

法定追認となるのは以下の行為です。
①全部又は一部の履行
②履行の請求
③更改
④担保の供与
⑤取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
⑥強制執行

ということです。

①全部又は一部の履行→履行するということは契約の存在を前提としているので自動的に追認してることになる!
②履行の請求→請求するということは契約の存在を前提としているので自動的に追認してることになる!
③更改→契約内容の変更のこと。「変更しましょう」ということは契約の存在を前提としている(以下同)
④担保の供与→自身の財産に抵当権や質権等の担保物件を設定すること。設定するということはその前提となる
被担保債権を認めていることになるので自動的に追認していることになる!
⑤取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡 →契約がなければありえない(以下同)
⑥強制執行→前提となる契約がなければありえない!(以下同)
まとめ


