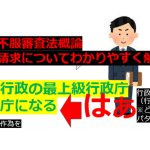この記事は「行政不服審査法の教示義務・執行停止」ついて
行政書士試験対策向けにわかりやすく解説しています。

(行政庁の)教示義務

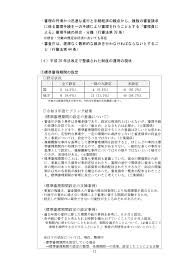
教示:行政庁が、不服申立て制度などの存在等について、処分の相手方などに知らせる制度です。

知らせてねーーー」っていう通知ですね。それを「教示」と言います。
行政庁が教示すべき場合
①行政庁が、(その処分の相手方が)不服申立てをすることができる処分を書面でする場合(当該処分を口頭でする場合は不要)(82条1項)
不服申立てをすることができる旨、
不服申立てをすべき行政庁、
不服申立てをすることができる期間について教示することになっています。
※不服申立て:審査請求・再調査の請求又は他の法令に基づく不服申立ての総称。
訴訟の場合は不服申し立てとは言わない。

不服申し立てはここに言ってね!(不服申し立てすべき行政庁)、
不服申し立てするならここまでにしてね!(期限がくると不服申し立てができなくなる)
②行政庁に利害関係人から教示の請求がある場合(82条2項)
当該処分が不服申立てをすることができる処分であるかどうか、
(ここだけが違うだけで、もしできないならできない!で終わり。
できるなら・・・↓)
できる場合は、
不服申立てをすべき行政庁、不服申立てをすることができる期間について教示します。
(これは①と同じ)
教示ミスの救済措置

行政庁が「不服申し立てできる旨」等を名宛人にお知らせ忘れたり、
間違った情報を伝えたりする場合があります。(人間ですからね・・・)
その場合、行政庁のミスにより名宛人が不利益を被らないために
「教示ミスの場合の救済措置」がきちんと設けられています。
教示をしなかった場合、当該処分について不服がある者は、当該処分庁に不服申立書を提出することができ、
当該処分が処分庁以外の行政庁に対し審査請求をすることができる処分であるときは、
処分庁は、速やかに、当該不服申立書を当該行政庁に送付しなければならない(83条1項・3項)。

でも不服申し立てしたい!!!
でも教示されてないしどこに不服申し立てすればいいかわからん!
だったら処分庁(その処分を課した行政庁)に不服申し立て書出すか・・・
↓
実際は、不服申し立てすべき行政庁が処分庁でない場合、
その不服申し立てをもらった処分庁はただちに正しい
「不服申し立て受け入れ先の行政庁」に書類を送付しないとダメ
当たり前じゃん、教示すべきなのに教示してないのは行政庁なんだから
それくらいはやってよ!っていうカンジ。
基本的に、何度も言うけど、行政法は行政の暴走を阻止するために
作られているので、基本的に国民の不利益になるようなことにはなってないんですね!
<復習>
・審査請求は行政庁による裁判所ごっこ(ごっこといってもきちんとした法律で認められた手段ですよ)
<不服申し立て適格>
・処分の審査請求の不服申し立て適格:法律上の利益を有する者
・不作為の審査請求の不服申し立て適格:その申請をした者<審査請求先>
・基本最上級行政庁(処分庁の最上級行政庁が審査庁になるということ)
・処分庁が最上級行政庁の場合は、その最上級行政庁自身(処分庁が審査庁になるということ)
・個別法に規定がある場合は、その法律に定める行政庁(処分庁がどこであれ、その法律に定められた行政庁が審査庁になるということ)
審査請求をすることができる処分につき、処分庁が誤って審査請求をすべき行政庁でない行政庁を審査請求をすべき行政庁として教示した場合において、
その教示された行政庁に書面で審査請求がされたときは、当該行政庁は、速やかに、審査請求書を処分庁又は審査庁となるべき行政庁に送付し、
かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない(22条1項)。

教示:「審査請求すべき行政庁はAね!!(本当は行政庁B)」
名宛人:Aに審査請求書出す
行政庁A:教示ミスってるやん、Bやん!Bに送付!
&
行政庁Aは名宛人(審査請求したのだから審査請求人ともいう)に対して
「教示がミスってたのでAって教示してたけどホンマはBに審査請求せなあかんから、 Bに審査請求書を再送付しといたで!!よろしく!!!」
執行停止・執行不停止の原則

審査請求がされても、処分の執行が停止されることは基本的にはないです。
=審査請求しても執行「不停止」の原則
つまり、審査請求しても、処分は引き続き行われ続けますよってことです。
審査請求がなされても、行政の円滑な運営のために係争処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない(25条1項)。

基本的には処分は名宛人がおかしいから処分されてることがほとんどなので、
審査請求のたびに処分の執行停止をしてたら、
「とりあえず審査請求だけしておいて、処分を免れよう」とする人が出てくるでしょ。
それはダメですね。
例外:執行停止される場合
職権による執行停止
「処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁」は、必要があると認める場合には、
職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止「その他の措置」をとることができる(25条2項)。

つまり処分庁のボス(会社でいう上司)、処分庁の審査庁(会社でいう審査部とか法務部)は「この処分はあまりに厳しすぎでしょー」とか
思ったら「うーーん、これはひどい処分だしいったん処分停止で!」とかって判断できるよってこと。
職場のボスが部下の失敗を強制停止するカンジを想像してもらえればいいかな!
申立てによる裁量的執行停止
名宛人から「執行停止」の申し立てがある場合は、
(基本的にはもちろん執行不停止なんだけど)
処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、
処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止「その他の措置」をとることができます。

行政庁の判断次第ってことですね!
「処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁」は、必要があると認める場合には、申立てにより、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止「その他の措置」をとることができる(25条2項)。
「処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない審査庁」は、必要があると認める場合には、申立てにより、処分庁の意見を聴取した上、執行停止をすることができる。ただし、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止以外の措置をとることはできない(25条3項)。
申立てによる義務的執行停止
名宛人から「執行停止」の申し立てがあって、
処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるときは、
(基本的にはもちろん執行不停止なんだけど)
審査庁は、執行停止をしなければなりません。(義務)
ただし、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、
又は本案について理由がないとみえるときは、執行停止しなくてもいいです。
申立てがあり、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるときは、審査庁は、執行停止をしなければなりません。ただし、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、この限りではない(25条4項)。

「あーたしかにこの処分やり続けたら名宛人にめっちゃくちゃ不利益あるなーーー」と明らかな場合は
審査庁は義務的に執行停止「しなければなりません」。
当たり前ですよね!もしこれで執行停止しなければ取り返しのつかないようなことに
なっちゃう場合なんですから。そりゃ一時処分ストップ=執行停止 させます。
ただし・・・
それによって公共の福祉に重大な影響を及ぼすのであれば・・・
みんなの迷惑のほうが当然優先されるので(みんなの迷惑にならないようにしないとなので)
執行停止しなくてもいいってことです。
執行停止中「処分の効力の停止」は、処分の効力の停止以外の措置によって目的を達することができるときは、することができない(25条6項)。
「処分の効力の停止」というのは、そもそも処分がない状態に戻すってこと。
つまり結構重大な判断になります。
なので、処分の効力の停止を行うのは、処分の効力の停止以外の選択肢が他にない場合のみに限られるということです。
例:懲戒免職処分の効力の停止
懲戒免職処分なんてものは、そもそも懲戒免職処分自体をなかったことにしなければ、
名宛人の不利益は回復できない場合が多いですね。
執行停止をした後において、執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすことが明らかとなったとき、その他事情が変更したときは、審査庁は、その執行停止を取り消すことができる(26条)。
執行停止した後でも、(執行停止によって)公共の福祉に重大な影響を及ぼすことが明らかになったり、
他事情が変更した場合は執行停止を取り消せるよ!っていう例外規定です。
執行停止したらずーーーっと執行停止し続けなきゃいけないなんてわけではないですよ、ということです。
まとめ:
・教示義務(行政庁の教示義務)
教示とは、行政庁が不服申立て制度などの存在について処分の相手方に通知する制度です。
処分を受けた者に対し、不服申立てができる期間や方法について通知するものです。
通知内容としては、不服申立てができる旨、申立て先の行政庁、不服申立て期間が含まれます。
・教示ミスの救済措置
誤った行政庁が教示された場合、審査請求書は正しい行政庁に送付されます(22条1項)。
教示された行政庁が誤りだった場合でも、名宛人が教示された行政庁に審査請求書を提出すると、正しい行政庁に送付されます。
・執行停止・執行不停止の原則
審査請求をしても、基本的に処分の執行は停止されません。
執行不停止が原則で、審査請求中も処分の効力や手続は続行されます(25条1項)。
[解説] 審査請求の度に処分の執行を停止すると、悪用の可能性があるため原則停止しません。
・例外:執行停止される場合
特定の条件下では、処分の執行停止が可能です。
・職権による執行停止
「処分庁の上級行政庁」や「処分庁である審査庁」は職権で執行停止が可能(25条2項)。
必要と認められる場合、処分の一部または全部の効力や手続の停止などの措置が取られます。
・申立てによる裁量的執行停止
名宛人が執行停止を申し立てた場合、処分庁の上級行政庁や審査庁が停止を判断できます(25条2項)。
・申立てによる義務的執行停止
緊急に重大な損害を避ける必要がある場合、審査庁は執行停止を行う義務があります(25条4項)。
ただし、公共の福祉に重大な影響を与える場合や、本案に理由がない場合は停止しなくてもよい。
・執行停止中の注意事項
処分の効力の停止は、他の措置で対応できない場合に限られます(25条6項)。
・執行停止の取り消し
執行停止後、公共の福祉に重大な影響が判明した場合などは、執行停止を取り消すことができます(26条)。
執行停止の判断が変更される場合、審査庁は停止の取り消しを行うことが可能です。
[解説] 執行停止は永久的なものではなく、状況の変化によっては取り消されます。